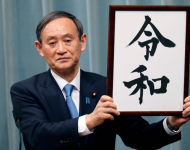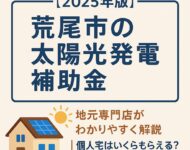目次
熊本の実例でわかる|ソーラーパネル10年後の状態と発電量
これから設置を検討されている方へ。
「営業マンに『パネルは壊れません』と言われたけど本当?」「元を取る頃に故障が出る?」「10年後に撤去が必要?」「屋根に付けて壊れたら大変?」——こんな不安に、熊本の実例と実データでお答えします。
結論:可能性はゼロではありません。しかし、正しい選び方と点検の考え方を知れば不要な不安は大きく減らせます。熊本弁の「安物買いの銭うして(捨てる)」が起きないよう、長期視点での製品・施工・監視選定が大切です。
⒈ 10年以上経ったパネルの現状は?—“見える化”が鍵
住宅用は10〜30枚程度で比較検証が難しいため、本記事では枚数の多い発電所の事例で原理を解説します。「パワコンの電圧だけ見ればOK?」というのは不十分。1枚ずつ外して測るのも現実的ではありません。
一括で状態把握する王道:サーモカメラ(熱画像)
- 上空(または俯瞰)からパネル群を熱画像でスキャン
- 色のムラ=温度差が異常のヒント
- 計器では見えない表面の異常発熱を広範囲で短時間に把握
⒉ 真相を暴く3つの検査:サーモ/IVカーブ/EL試験
- サーモカメラ:効率が高く、現場での一次スクリーニングに最適
- IVカーブトレーサー:発電回路の健全性を物理量で解析(読み取りは専門性が高い)
- EL試験:セル割れ等が画像で直感的に判別。ただし装置が高価で屋根上運用は非現実的
結論:まずサーモで広く“あたり”を付け、必要に応じてIV/ELで深掘りするのが費用対効果と精度のバランスに優れます。
⒊ ホットスポットとは?—局所加熱は要注意サイン
ホットスポットは、セル(約15cm角)やジャンクションボックス部分が周囲より異常に高温になる現象。直ちに発電量低下と一致しないケースもありますが、劣化や故障の予兆として要監視です。
パネル内ストリング・ホットスポット
1枚のパネル内部は多くが3つの回路(ストリング)。横一帯(約1/3)が高温化=内部ストリングの不調の疑い。外観は正常でも熱で差が出るのがサーモの強みです。
⒋ 回路(ストリング)単位のホットスポット
住宅用では10〜20枚を直列接続します。例えば18枚直列の全枚が周囲より高温というケースでは、工事起因や接続・部材の問題の可能性。原因究明には切り分け作業が必要で、手間と安全管理が重要です。
⒌ 実データで検証:不具合発生率の比較
各メーカーのパネルを巡回監視した結果(サーモ調査ベース):
- 計15,601枚中、不具合の可能性82枚 → 約0.53%(≒200枚に1枚)
- REC Solarの調査:計175,583枚中、20枚 → 約0.01%(約1万枚に1枚)
サンプル数が多いにも関わらずRECは検出率が桁違いに低いという結果。
※本記事の数値・画像はREC Solar公式ブログの資料を基に、メーカー承諾の上で引用・再構成しています。
当社の「3つの安心保証」について
⒍ 10年超の発電量はどうなる?—“ばらつき”を見る
実際の発電所データ(弊社施工も含む)では、メーカーA(8年経過)はモジュール間の発電量にばらつき、REC Solar(9年経過)は相対的にばらつきが小さい傾向が見られました。
“見える化”で保全を前倒し
モジュール単位の可視化ができる最適化機器(例:パワーオプティマイザ)を採用すると、不調の特定や影響の緩和がしやすく、長期の発電損失を抑制できます。
⒎ 熊本ならではの劣化要因と対策
- 黄砂・火山灰:表面堆積→散乱光ロス。定期洗浄や防汚コーティングの適否検討
- 台風・豪雨:架台・固定金具・配線の緩み/浸水点検
- 高温多湿:PID/LIDなど出力低下加速リスク→通気性確保と機器選定が重要
⒏ 10年目に必ずやるべき点検(基礎)
- 外観:割れ・反り・汚れ・ケーブル被覆・端子部・接続箱
- 電気:絶縁・接地・IVカーブ
- 熱画像:サーモで面のムラと局所高温をチェック
- ログ:モジュール単位の発電履歴と落ち込み箇所の特定
※費用・所要時間は規模と屋根形状で変動します。事前見積と点検項目の明示を依頼しましょう。
⒐ 失敗しない“選び方”チェックリスト
- 製品:長期の出力保証/機器保証の実態(条件・免責)
- 実績:10年級の追跡データや熱画像の例を提示できるか
- 監視:モジュール単位の見える化・影対策の提案力
- 施工:メーカーの認定制度(例:RECのプロフェッショナル制度)に登録か
- 回答力:「なぜそのパネルを勧めるのか?」に即答できるか
⒑ 無料相談・点検のご案内(熊本エリア)
「押しの強い営業はしません」。女性スタッフが丁寧にご案内します。
タケモトデンキ㈱ 代表取締役 竹本雄一
関連記事
弊社へのお問い合わせは コチラです!(^_^)/
弊社の豊富な施工例は コチラから!(^_^)/
TVCM(コンセント壊れちゃった編)は コチラから!(^_^)/
TVCM(タケモトデンキ 社長編)は コチラから!(^_^)/
私の会社へかける熱い想いは コチラから!